あなたがこのページをご覧になっているということは、すでにご自身が坐骨神経痛ではないかと疑っておられるのだと思います。
そのため貴重な時間を使ってインターネットで検索し、このページへお越しになったのでしょう。
はじめにあなたへお伝えしたいことは、坐骨神経痛とはどういったものなのかを正しく知って頂きたいということ。
次に、坐骨神経痛の原因や症状を理解することで、あなたに合ったよりよい治療方法を選ぶことができるということ。
最後に、坐骨神経痛をこれ以上進行させないためには、予防する方法があること。
この3つについてご理解いただきたいと思います。
それでは早速ですが、カラダの専門家である柔道整復師があなたへ坐骨神経痛の正しい知識からお伝えしていきます。
目次
坐骨神経痛とは病名ではありません

よく耳にする「坐骨神経痛」という言葉。
カラダの専門家でなくても、日常会話の中で耳にすることもありますね。
友人や同僚、家族の間で「お尻のあたりが痛くて」とか「脚が痛くて」というような話をすると、誰かが「それ、坐骨神経痛じゃない?」と言ったりすることがあります。
このように坐骨神経痛という言葉は、一般的にも知られている「糖尿病」などを表す「病名」と同じように使われていることが多いです。
しかし、坐骨神経痛という呼び名から正しい理解が必要なのです。
というのも、坐骨神経痛という呼び名は「病名」ではありません。
坐骨神経の通り道(お尻、太もも、膝から下、足の指先)に出てきた、痛みやしびれが続く状態を総称し、このように呼んでいます。
では、総称して呼んでいる「坐骨神経」とは、私たちのカラダのどの部分にあるのでしょうか?
(1)坐骨神経
坐骨神経は、お尻の筋肉を抜けて足先へ向かう「末梢神経」のひとつです。
末梢神経は脳から指示が出された命令を、カラダの隅々まで伝える大切な伝導経路であります。
この伝導経路は次の3つがあります。
[1]運動神経脳から命令を送り、カラダの各部分を動かす神経
[2]知覚神経温度や痛みの感覚を、皮膚や筋肉、関節を介して伝える神経
[3]自律神経無意識で内臓や血管などを調整し動かす神経
坐骨神経があるからこそ、私たちはバランスを取りながら「歩く」「座る」「立つ」という複雑な動きを自動的に行うことが出来ているのです。
(2)坐骨神経は意外に長い
坐骨神経はイメージよりも太くて長いのが特徴です。
医学的には、ボールペンくらいの太さがあり、1メートルくらいの長さがあると言われています。
このような太くて長い坐骨神経。
カラダの正面部分は、太股の外側から膝へ、膝から脚の親指へ伸びています。
スポーツウェアのスパッツなどで、この部分に少し強度を持たせたサポーターのような仕組みが入っていることもあります。
カラダの背中方向は、お尻の少し上から太股の裏側を通り、ふくらはぎの外側へ向かって伸びています。
いかがでしょうか。坐骨神経は下半身の中でも、脚の部分の大半に巡っている神経なんですね。
坐骨神経痛の原因は?

坐骨神経痛には、次の3つの代表的な原因があります。
(1)腰椎椎間板ヘルニア
若年層の方に坐骨神経痛が起こった場合の原因として多いです。
小さな骨が重なることで腰椎が出来ていますが、この小さな骨と骨の間にあるクッションの役割をしている「椎間板」の中にあるゼリー状の物質が何らかの影響で飛びだすと、腰椎の中を通っている神経が圧迫され痛みやしびれが起こります。
(2)腰部脊柱管狭窄症(ようぶせきちゅうかんきょうさくしょう)
高齢の方に坐骨神経痛が起こった場合の原因として多いです。
腰のあたりにある神経が通るすき間(脊柱管と呼びます)が加齢によって狭くなり(狭窄)神経が圧迫されることで痛みやしびれが起こります。
(3)梨状筋症候群
お尻の奥にある筋肉に「梨状筋(りじょうきん)」と呼ばれる筋肉があります。この筋肉には坐骨神経が走っているため、事故などの外傷や激しいスポーツによって神経が圧迫されると、痛みやしびれが起こります。
また、これら3つ以外にも、坐骨神経痛が起こる原因があります。
それは疾患による原因。
坐骨神経付近に腫瘍などができることで、神経が圧迫されているということもあります。
坐骨神経痛の症状とは

坐骨神経痛の症状には、次のような痛みやしびれがあります。
(1)立っていると脚が痛くて、立っていることが辛い
通勤のときや、お仕事で立っている時間が長い方には大変厳しい症状です。
(2)カラダをかがめると痛い
靴下を履こうとしたときや、玄関で靴を履こうとしたとき。
ちょっとカラダをかがめただけなのに痛みを感じることがあります。
(3)寝ていても痛い
安静にしていても脚やお尻のあたりが痛い、しびれるということもあります。
(4)腰が痛い
腰痛は坐骨神経から来ていることもあります。
坐骨神経痛は、下肢部分に
- 痛み
- しびれ
- 張り
- 締め付け
このような症状として表れることがほとんどです。痛みやしびれが続いているようなら、あなたが坐骨神経痛を疑っているのは正しいかもしれません。
また、ここで一つ用心しておいて頂きたいことをお伝えします。
それは、高齢者の方の場合、坐骨神経痛の症状によって動くことが億劫になり、肥満や足腰に衰えが出てしまう場合があることです。
最近耳にすることが増えた「ロコモ」の心配も出てきますので、痛みやしびれは放置せず治療して頂きたいのです。
治療することで、
「痛みやしびれで運動しない→筋力低下→自立した生活の低下」
という負のサイクルを抜けだし
「痛みやしびれを治療→動ける自分→自立した生活の向上」
を目指すことができるのです。
高齢者の方の坐骨神経痛は、不自由な生活を引き寄せるきっかけにもなりかねませんので、気をつけていただきたいと思います。
坐骨神経痛の治療法

坐骨神経痛の治療には大きくわけて5つの方法があります。
(1)物理療法
あなたのライフスタイルに合わせた治療方法です。
外科的な治療ではありませんので、入院などは必要ありません。
マッサージや温熱機器を使って血行を良くし、痛みやしびれをやわらげる治療を行います。
私たち柔道整復師が得意とする治療方法です。
(2)運動療法
軽い運動をすることで、痛みやしびれの改善を図ります。
痛みやしびれが激しくない方向けの方法です。
(3)装具療法
コルセットなどを使って固定することで痛みやしびれをやわらげる方法です。
これは短期間だけ利用するのならいいのですが、いつまでもコルセットを付けていると筋力が低下することもあり、今度は自分の筋肉でカラダを支えることが難しくなることもあります。
一時的な解消法として使うのがベストです。
(4)薬物療法
整形外科へ行き、お薬をもらって痛みやしびれを解消する方法です。
根本的な原因を治療することはできませんが、激しい痛みで日常生活に支障が出そうな方は選んでいただきたい治療法です。
(5)ブロック治療
こちらも整形外科での治療となります。
激しい痛みで生活が出来ない。仕事へ行けないという場合、まずは痛みやしびれを解消することが先決です。
そうでないと、根本原因の治療もできません。
このような場合は、整形外科で一時的に痛みやしびれを解消するお薬を注射してもらうことができます。
整形外科の先生と相談して利用するかどうかを検討してみてください。
痛みやしびれは、かゆみと同じくガマンできるものではありません。
生活に支障が出そうなことを解消した後、ゆっくりと落ち着いた気持ちで根本原因の治療を行って頂きたいと思っています。
坐骨神経痛は予防できる!

坐骨神経痛は、普段の暮らしの中で少し気遣うことを続けると予防することも可能です。
(1)姿勢に注意しましょう
正しい姿勢をご存じでしょうか?
座っているとき、立っているとき、正しい姿勢をキープすることは予防に大変効果的です。
もしご自身の正しい姿勢がわからない場合は、お近くの整骨院へ相談してみてください。
カラダの専門家が、あなたに合った正しい姿勢の位置を教えてくれます。
(2)冷え予防
冷えると血行が悪くなり、痛みやしびれが起こりやすくなります。
膝掛け1枚でも使うように意識しましょう。
(3)ストレッチ
お風呂上がりにはストレッチをするのも効果的です。
お仕事中でも、凝り固まったカラダをストレッチしておくと、血行が促進されます。
(4)運動の継続
激しい運動でなくてかまいません。
肥満やロコモを意識した、軽い運動でかまいませんので継続していただきたいですね。
(5)盲点でもある靴
靴によってカラダのバランスが変わります。
歩きやすい靴を選ぶことで、予防することにもなります。
また、靴の底をみてください。片減りしている場合は、バランス良く歩いたり立ったりできていない可能性があります。
今のうちに姿勢を正しい位置に戻す努力をすることで、予防することもできます。
まとめ
坐骨神経痛は、ぎっくり腰とは違い「じわじわ」と痛みやしびれがやってくることが多いです。
そのため放置してしまう方もいらっしゃるのですが、早めの解消を目指された方が、後々カラダへの負担も軽減されます。
また、痛みやしびれは心への負担にもなりますので、スッキリとした毎日を送っていただくためには早期の治療は欠かせません。
特に高齢者の方は、これからの生活に大きな影響を与える原因にもなりかねませんので、痛いな、しびれるな、と感じられたときは迷わずお近くの整骨院や整形外科を訪ねて頂きたいと思います。
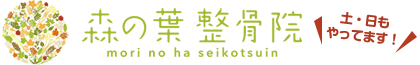





















上記のお悩みをお持ちでしたら、初回キャンペーンをご利用いただき、ぜひ森の葉整骨院の治療を体験してみてください!
一人でも多くの方の症状が改善し、痛くないことが当たり前である生活を取り戻していただきたい、そのために少しでもお役に立てればと思い、この整骨院を開院しました。
根治を目指して、私も患者様と一緒に闘います。
お困りごとやお悩みがあれば、ぜひお気軽にご相談ください。